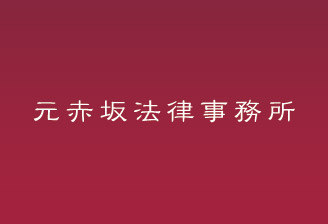

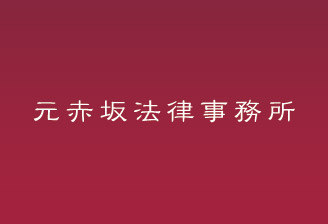


2019年6月現在
民法の相続分野(以下「相続法」と言います。)の改正が行われたことについては、様々な報道を通してご存じの方が多いと思います。改正相続法の施行日は、原則として2019年7月1日ですが、例外がいくつかあり、自筆証書遺言の方式緩和に関する規定は、2019年1月13日にすでに施行されています。
また、配偶者の居住の権利(配偶者短期居住権を含む)に関する規定は、2020年4月1日、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、2020年7月10日が施行日です。
文中の条文は、特に断りの無い限り、改正後の条文番号を掲載しています。
今回の相続法改正は、1980年(昭和55年)に配偶者の相続分が引き上げられ、寄与分制度が新設された以来の大改正となりました。これは、急激な少子高齢化社会が進み、相続開始時の配偶者の年齢が高くなり、高齢配偶者の生活を保護する必要性が高まる一方、子については、すでに成人、経済的に独立している場合が多くなったという社会経済情勢の変化を踏まえたものです。
今回の相続法改正の重要点を、改正趣旨から3つに大きく分類すると以下のとおりになります。
配偶者保護のための改正
(1)配偶者の居住権を保護するための2つの制度の創設
(2)持戻し免除の意思表示の推定規定の創設
遺言の利用を促進するための改正
(1)自筆証書遺言の方式の緩和
(2)遺言執行者の権限の明確化
(3)「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づく保管制度の創設
利害関係人(相続人を含む)の実質的公平を図るための改正
(1)遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
(2)相続人以外の者(例えば被相続人の介護をした、相続人の配偶者など)の貢献を考慮するための制度の創設
なお、その他にも改正点はありますが、使用を検討する方が多いと思われる制度に絞っています。
遺留分に関する改正
遺留分を侵害した場合の処理が、遺留分を侵害した側が、遺留分権者に対し、「現物の分割譲渡をする」のではなく、金銭で支払うことになりました。
このことは、相続対策をするに際し、特に注意しなければならない改正です。
1. 配偶者居住権について(民法1028条~1036条)
(1)制度創設の趣旨
配偶者居住権は、被相続人(死亡した人)の配偶者が、終身又は一定期間、被相続人が所有し配偶者が住んでいた建物に、無償で継続して住み続けられる権利です。
改正以前、被相続人の配偶者がこれまでどおり居住建物に住み続けるためには、①遺産分割により配偶者が建物の所有権を取得するか、②建物の所有者となった者から賃借権の設定を受けるなどの方法がとられていました。
しかし、これでは、共同相続の場合、①の方法で建物を取得した配偶者は、預金など他の遺産を取得できず、生活に支障が出ることがありましたし、②の方法は、長期にわたる賃料の支出で配偶者の生活にやはり相当な負担がかかっていました。そこで、配偶者居住権という制度が創設されました。
(2)改正内容
配偶者居住権は、①被相続人の配偶者が、②相続開始時(被相続人が死亡した時)に、③被相続人が所有する建物に居住していた場合(①から③全て充たす必要があります)、
④その建物全部について、⑤配偶者が無償で使用及び収益することができる権利 です。配偶者と被相続人との同居は要件ではありません。
(3)存続期間
原則、配偶者の終身の間です(1030条)。
(4)配偶者居住権の取得方法 は、
①遺産分割協議(家事調停を含む。)②遺贈(遺言でする贈与)、③死因贈与(死亡した時に贈与することを生前、受贈者との間で契約しておくこと)、④遺産分割審判のいずれかとなります(1028条、554条、1029条)。単に、相続させる旨の遺言によって取得することはできないので注意が必要です。
また、被相続人と、配偶者以外の第三者が共有する建物については、第三者の負担が大きいので、配偶者居住権は取得できません(1028条1項但し書き)。ただし、当該建物が被相続人と配偶者の共有の場合は、対象となります。
なお、配偶者居住権を、前述のとおり、遺贈や死因贈与で取得することはできますが、配偶者居住権の財産評価の方法が現時点で確立されておらず、財産評価が相当難しくなると予想されています。配偶者居住権が遺留分侵害額請求の側面で現れる際にも、財産評価方法が確立されていないことは問題となってきます。従って、財産評価方法が確立していない今の段階で、この権利を遺贈や死因贈与の対象とすることは相当の危険が伴うといわれています。遺産分割協議の場合も、何らかの目安が無ければ協議が困難と考えられており、財産的評価の方法の早期確立が望まれます。
(5)配偶者居住権の民法上の注意点
① 介護サービス住宅等に転居される場合
配偶者居住権は、配偶者の居住の継続を目指すためものであるため、たとえ建物所有者が承諾しても権利は譲渡できませんし、買取請求権もありません。
ただ、高齢となり自力で生活できなくなった配偶者が、バリアフリー介護サービス付住宅や介護施設に入るような場合、配偶者居住権を換価できたら配偶者のためにもなると言えます。
そこで、遺言や死因贈与、遺産分割協議において、事前に、一定の場合に買取請求ができる旨とその金額(もしくは金額の算定基準)を定めておくことは可能とされております。
この制度を検討する場合には、是非、ご検討ください。
② 配偶者居住権で居住する配偶者の義務
配偶者居住権を有する配偶者には、従前の用法を遵守する(以前と同じような使いかたをする)義務及び善管注意義務、配偶者居住権の譲渡禁止、無断の増改築・第三者の使用収益の禁止(但し、所有者の承諾を得て第三者に使用収益させることは可能)などの義務があります(1032条、1036条)。
③ 配偶者居住権の対抗要件と対抗力の範囲
借家権とは異なり、配偶者居住権の対抗要件は登記です(不動産登記法3条9号)。法律自体で登記請求権が認められており、共同申請(不動産登記法60条)なっています。
配偶者居住権の対象は、建物だけであり、敷地については対象ではありません。従って、登記は建物についてなされ、対抗力も建物についてのみ生じます。
そこで、敷地所有権の譲受人、敷地を差し押さえた者、敷地の抵当権者には、登記の先後を問わず対抗できません。
(6)配偶者居住権の税法上の注意点
配偶者居住権の財産評価の方法が現時点で確立されているとまでは言えず、財産評価が相当難しくなると予想されています。
配偶者居住権が遺留分侵害額請求の側面で現れる際にも、財産評価方法が難しくなることが予想されます。これを素人がするのは困難であると言えます。
そこで、配偶者居住権を使用する場合には、税法の専門家に相談されることをお勧めします、
2. 配偶者短期居住権について(民法1037条~1041条)
(1)創設の趣旨
配偶者短期居住権は、前述の配偶者居住権の帰趨が決定するまでの、いわば応急の権利です。被相続人の配偶者は、一定期間、無償で居住建物を使用することができます。ここでは、前述の配偶者居住権との比較を指摘するに留めます。
(2)配偶者短期居住権の内容
配偶者短期居住権は、①配偶者が、②被相続人の所有建物に、③相続開始時(被相続人死亡時)に、④無償で居住していた場合(①から④全て充たす必要があります)、配偶者に⑤一定期間無償で使用することを認めるものです。なお、配偶者居住権と同様、被相続人と配偶者の同居は要件とはされていません。
(3)存続期間
①遺産分割がなされる場合は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日まで(ただし、最低でも相続開始から6ヶ月を経過する日)、
②遺産分割以外の場合は、居住建物を取得した者の、配偶者短期居住権の消滅の申し入れの日から6ヶ月を経過する日までです。
(4)注意点
① 配偶者居住権と異なり、この権利は、法律上当然に発生します。なお、配偶者が、相続開始時に前述の配偶者居住権を取得したときや、欠格事由に該当しもしくは廃除により相続権を失った場合、この権利は発生しません。
② 配偶者居住権と異なり、配偶者短期居住権は、配偶者への生前贈与や遺産の分割とは扱われず、配偶者の具体的相続分や遺産分割における取得分に影響しません。生前贈与等ではないので、遺留分の侵害が問題になりません。
③ 配偶者居住権と異なり、この権利は、建物全部についての無償の使用権ではありません。居住建物の一部を無償で使用していた場合、その部分についてのみ、この短期居住権を取得します。また収益権はありません。
④ 配偶者居住権と異なり、登記による対抗要件の制度はありません。
配偶者居住権も配偶者短期居住権も、少子高齢化時代の高齢配偶者の保護という視点から優れた制度といえます。特に、配偶者居住権は、居住建物の所有権を取得するよりも低廉な価格で配偶者の居住権を確保できるという大きなメリットがあると言われています。しかし、前述のとおり、配偶者居住権の財産評価基準が定まらない段階での利用は、配偶者とその他の相続人との間で居住権の財産評価を巡り激しい対立や新たな紛争を生む可能性が有り、制度を利用される場合には、利害得失につき事前に弁護士など法律の専門家に是非ご相談ください。
3. 持戻し免除の意思表示の推定規定の新設(903条4項)
―配偶者に賃貸マンション等を贈与・遺贈した場合―
(1)制度趣旨
婚姻期間が長期にわたる場合の贈与や遺贈は、配偶者の長年にわたる貢献に報いると共に、老後の生活保障の趣旨で行われることが多いといわれています。
しかし、903条1項で定める特別受益の持戻し(特別受益の持戻しとは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、あるいは生前に婚姻のためや生計の資本として贈与を受けた人がいた場合、その受益分(もらったもの)を遺産分割の際に相続開始時の相続財産に戻して各相続人の相続分(額)を計算し直すこと)が行われると、被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されないことになります。
そこで、このような事態を回避し、配偶者の権利の保護を図るのが、新設された持戻し免除の推定規定の趣旨です。
(2)改正内容
① 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人(死亡した人)が、
② 他の一方に、
③ 居住用建物又はその敷地を、
④ 遺贈又は贈与したとき
(①から④の全てを充たす必要があります)、
持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます。
つまり、効果として、遺産分割に際して、配偶者への居住用建物又は土地の、贈与あるいは遺贈については、特別受益として扱わずに計算する(持戻しをしない)ことになります。
この903条4項は、配偶者居住権が遺贈(死因贈与も含む。)された場合にも準用されます(1028条3項)。
なお、この規定は、推定規定ですから、他の相続人が、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていないことを立証すると、推定はくつがえり、特別受益分の持戻しをして計算することになります。
(3)特別受益の持戻しがされる場合と持戻しがされない場合の差異
例えば、相続人が配偶者と子2名の事例で、居住用不動産4000万円とその他の遺産が6000万円とします。被相続人が配偶者に居住用不動産を生前に贈与した場合について、特別受益の持戻しがされる場合と持戻しがされない場合の差異を説明します。
① 特別受益権の持戻しがなされた場合
その他の遺産6000万円に持戻された不動産4000万円を加えた合計1億円が相続財産となります。配偶者の法定相続分2分の1をかけて、5000万円が、配偶者の取得すべき相続分なので、配偶者は、すでに取得済みの居住用不動産(4000万円)及び他の遺産1000万円が、配偶者の具体的相続分となります。
② 特別受益権の持戻しがされない場合
これに対し、持戻しがされない場合(新設の903条4項が適用される場合)、配偶者の相続分は、6000万円の2分の1の3000万円となります。配偶者は、居住用不動産(4000万円)のほか、他の遺産3000万円の合計7000万円を取得します。
このように持戻しが免除されると、配偶者の居住不動産も確保し、さらに生活資金も確保できることになります。
(4)改正法の持戻し免除の意思表示の推定規定は、
① 婚姻期間が20年以上の夫婦で、
且つ、
居住用不動産の遺贈または贈与
に適用されます。
今後、社会情勢が変化すると、金銭等居住用不動産以外の遺贈や贈与に適用範囲を広げる必要性も考えられ、運用の集積を待ちたいと考えます。
4. 配偶者保護のための改正を踏まえた相続・資産活用(903条4項)
せっかく建築した耐用期間の長い住宅に、人生100年安心して幸せに暮らすために、専門家に相談しつつ、一つの方法として、配偶者居住権等を検討することをお勧めします。
1. 自筆証書遺言の方式の緩和
自筆証書遺言は、他の方式に必要な公証人や証人が不要で、遺言者が一人で作成できるので、特別な費用がかからず、簡便といわれています。
しかし、改正前は、偽造防止の観点からも、全文自書(原則自分で手書き)でなければならないとされ、また、文字を訂正するにも自書により厳格な方式によらなければならず、遺言者の負担が大きく、自筆証書遺言の簡便性を損なうことになっていました。
そこで、
① 民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律(以下、改正法)では、
自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言と一体をなす相続財産目録(遺言の対象とする財産のリスト)については手書きであることを要しない(968条2項)とし、遺言書の作成に関する遺言者の負担を軽減しました。
パソコンによる作成、代書のほか、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳のコピーを目録として使用することも可能です。但し、この場合、偽造などを防止するため、目録の各ページ(両面に記載があるときは両面)に遺言者の署名と押印が必要なので、注意が必要です。
② 自筆証書遺言の加除訂正の方式については改正されていないことに注意が必要です。(968条3項)。
自書によらない財産目録を加除・訂正するには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に押印をしなければなりません。
特に、パソコンで作成した目録の加除訂正、差替えには非常に注意が必要です。
例えば、「3000万円」と記載すべきものを「3000円」と記載してしまったとします。これを訂正するには、自書で、「万」を加え、「この行1字加入」と記載します。これが、場所の指示、変更した旨の付記あたります。そして、署名し、変更の場所に印を押します。
目録の差し替えは、さらに注意が必要です。差し替えは、全部を変えることになるので、訂正に自書を要求する968条3項の条文をそのまま当てはめると、差し替え後の目録は、自書が必要になります。しかし、これではパソコンで目録の作成を認めた意味がありません。
そこで、目録を差し替えるときには、まず、古い目録を外さずに、加除訂正がされたことを明確にします。その上で、古い目録の全部について斜線を引くなどし、その脇に押印し、かつ、欄外や遺言書本文に「目録◯ページ全部を削除」などと自書で付記し、署名をします。次に、新しい目録には、各ページに署名と押印をし、かつ、加除訂正による目録であることを示すため、新しい目録の表題を、「訂正後目録」などとして脇に押印をし、さらにその欄外や遺言書本文に自書で「目録◯ページを追加」等と付記して、その脇に署名するといった方法をとります。
加除訂正があるときは相当注意が必要ですので、遺言を無効にしないためにも、是非、専門家の方に、加除訂正の方式が正しいかどうかを相談されることをお薦めします。
なお、自筆証書遺言の方式の緩和に関する規定は、すでに2019年1月13日に施行されています。これから自筆証書遺言を作成する方は、目録については緩和された方式を使うことができます。
2. 法務局における自筆証書遺言の保管制度(施行日は2020年7月10日)
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。この制度により、遺言書の未発見、隠匿や変造を防止することができ、遺言者の最終意思の実現や相続手続の円滑化が期待されています。
(1)保管申請
① 遺言者がこの保管制度を利用するためには、遺言者が自ら法務局に行き、遺言書を無封の状態で保管申請をする必要があります。
② 遺言書保管官は、本人確認と、遺言書が所定の方式を満たすかどうかの形式的な審査をします。この審査により、遺言書の方式と申請時の遺言書の現状が確認されるので、死後の、家庭裁判所による検認は不要になります。
なお、この審査は形式的な審査であり、遺言の有効性を確定させるものではないため、遺言者の判断力に疑義がある等、遺言の有効性に疑義が生じ得る場合には、専門家と相談されることをお勧めします。
③ 申請した遺言者は、いつでも遺言書の閲覧や返還請求をすることができ、遺言者が死亡した後は、何人も遺言書保管官に対し、自分が相続人、受遺者や遺言執行者などに該当する遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。遺言者が死亡した後は、何人も遺言書保管官に対し、自分が相続人、受遺者や遺言執行者などに該当する遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。
3. 遺言執行者の権限の明確化
新法は、遺言執行者(被相続人の死亡後、遺言した内容を実現するため定められた事務を行う権限がある人)の権限を明確化して、遺言内容の円滑な実現を図ることとしました。
4. 遺言執行者の権限の明確化について
従来、その権限が明確でなく、争いの原因になっているという指摘があった、遺言執行者(被相続人の死亡後、遺言した内容を実現するため定められた事務を行う権限がある人)の権限が、明確化されました。
(1)遺言執行者の任務
遺言執行者は、中立の立場であることが求めらます。
遺言執行者は、その任に着いたら直ちに、その旨および遺言の内容をすべての相続人に通知します。
遺言執行者の任務は、遺言者の意思をその死後に実現することですから、遺言執行者が行った意思表示は、相続人に対して効力を生じます(1015条)。
(2)遺言執行者の権限の明確化(1012条1項)
①遺贈(お世話になった方に一定の財産を与えること)がされた場合は、遺言執行者が遺贈義務者となる。
②遺産分割方法の指定がされた場合、遺言執行者は、受益者に対抗要件を具備させるために必要な行為を行うことができる。
③預貯金について遺贈又は遺産分割方法の指定がされた場合、遺言執行者は、預貯金を払い戻して、受益者へ引き渡すことができる。
4. 遺言の利用を促進するための制度
遺言とは、自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について、ご自分の最終意思を明らかにするものです。遺言がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配がされます。
また、遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが、遺言の中で、日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば(遺贈)、相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。
このように、遺言は、被相続人の最終意思を実現するものですが、これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあります。
また、家族のあり方が多様化し、法定相続の規定をそのまま当てはめると実質的な不公平が生ずるような場合など、遺言が果たす役割はますます重要になってきています。
日本は、遺言の作成率が諸外国に比べて低いといわれていますが、今回の改正により、自筆証書遺言の方式を緩和し、また、法務局における保管制度を設けるなどしており、自筆証書遺言を使いやすくしています。
5. 公正証書遺言
公正証書遺言は、法律専門家である公証人の関与の下で、2人以上の証人が立ち会うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度です。遺言者は、遺言の内容について公証人の助言を受けながら、最善の遺言を作成することができます。加えて、遺言能力の確認なども行われますので、作成される方のニーズに応じて使い分けることができます。
ただ、自筆証書遺言の作成が容易になったことにより、判断能力が明晰だった頃に作成した公正証書遺言が、判断能力が不十分になった時点で作成された自筆証書遺言によって覆される可能性はあります。
遺言とは遺言者の人生における最終意思の発露
遺言は、遺言者の人生における最終意思の発露であり、遺言者の死亡によって効果が発生する法律行為です。
法定相続分と異なる割合で相続人に財産を残したい場合、遺言書を作成しておくと、法定相続分と異なる割合で相続人に財産を残すことができます。
1. 遺留分制度
(1)遺留分とは
遺留分とは、たとえば全財産を赤の他人や一部の相続人にあげるという遺言書があった場合、兄弟姉妹以外の法定相続人が、「家族なのだからせめて少しは私に残して」といえる権利です。
遺言が遺言者の最終意思であり、遺言により法定相続分と異なる指定ができるとはいえ、遺言者が財産の全てを自由に処分できるわけではありません。
例えば、妻と子供には一銭も財産をあたえず、その全部を赤の他人に譲るという遺言書が作成されたとします。
このような遺言書を残されると遺族の生活が困難になることも考えられ、相続制度が有する遺族の生活保障および被相続人の潜在持分権の清算という機能が害されてしまいます。
そこで、このような場合、遺族が「家族なのだから、せめてこれだけは残しておいて」といえる権利を法が認めました。これが従来の「遺留分減殺請求権」、改正法の「遺留分侵害額請求権」です。
(2)遺留分を持つ権利者と遺留分割合
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり(民法887条、889条、890条)、
遺留分割合は、
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
②それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1
となります。
(3)遺留分の算定
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定します(1029条)。
〔計算式〕遺留分=相続時の遺産+贈与した財産−相続債務
(厳密にはここから遺留分権利者が受けた贈与及び取得した相続財産を控除します)
2. 改正のポイント
(1)「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に
改正前は、
権利の行使により、遺産を構成する各財産について、目的物の一部(不動産や株式)の権利が、遺留分権利者に復帰して共有状態となると解されていたため、
不動産や株式の現物を分割取得させる方法が選択肢にありましたが、
改正法では、
遺留分権利者は、遺留分を侵害した相続人を含む受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と規定(1046条)したため、
① 遺留分に相当する現物を返還する方法は廃止され、
② 遺留分に相当する金銭を交付する方法のみ、が認められることになり、
名称も「遺留分侵害請求権」に変更されました。
(2)金銭調達のための期限を新設
上記金銭の調達のため、裁判所が期限を与える制度が新設されました(1047条5項)。
但し、受遺者が他に優良な財産を有している場合等、
請求者との合意により、遺留分に相当する金銭の弁済に代えて、他の財産を譲渡する「代物弁済契約」を締結することは妨げられません(482条)。
そのような、別途の合意がない限り、裁判所は、受遺者に対し、資金調達のための期限を与えることができます。
3. 遺留分の基礎となる生前贈与の範囲
(1)原則
改正前には、限定のなかった、遺留分算定の基礎となる、相続人に対する生前贈与(婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与)の範囲は、
改正により、原則として、「贈与時から相続開始時までの期間が10年を超えないもの」に限定(1044条3項)されます。
(2)例外
当事者双方が遺留分権利者に「損害を加えることを知って」贈与をしたときには、相続開始の10年前の日より前にしたものについても、遺留分算定の基礎とされます。
ただ、この例外要件の「損害を加えることを知って」の意味や適用については、かなり微妙ですので、遺言を作成する際、専門家に相談することをお勧めします。
契約を締結したのに債務者が契約上の義務を果たさない場合について、今回の債権改正法では、契約責任の現代化という要請に基づき、①債務不履行に基づく損害賠償の帰責事由の明確化(変容) ②契約解除の要件の見直し(債務者の帰責事由不要) ③催告による解除の制限と無催告解除の要件の明文化 ④危険負担の見直し(履行拒絶権への移行) ⑤売買契約の担保責任の全体的な見直しがなされました。
この部分は、大変難しい言葉が出てきて、また、違いがよくわからないような専門的な話も出てくる分野です。契約で、なにかトラブルが生じた場合に使う規定ですので、改正の指摘にとどめ、トラブルが生じたときは、早めに弁護士にご相談されることをお薦めいたします。
1. 債務不履行に基づく損害賠償の帰責事由の明確化について
(1)債務不履行の要件としての債務者の帰責事由
債務不履行の要件としての債務者の帰責事由債務不履行による損害賠償は、債務者に帰責事由(責めに帰すべき事由)がないときは免責されます。
このことは履行不能の条文にのみ規定されていますが(旧法415条後段)、同条前段(履行遅滞、その他)にも共通のルールと解されていることに争いはなく、条文と解釈に齟齬が生じていました。
また、旧法下では、帰責事由を「債務者の故意または過失及び信義則上それと同視しうる事由」と解するのが通説でした。
(2)改正法による債務者の帰責事由の明文化
改正法は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と明記しました(415条1項)。その帰責事由は、具体的には、当事者の合意した内容、目的、契約締結の経緯など一切の事情を考慮し、取引通念をも勘案して総合的に判断されます。
2. 債務の履行に代わる損害賠償(填補賠償)について
新法は、填補賠償が認められる場合を明確にしました。
債務の履行に代わる損害賠償が認められるのは、
①債務の履行が不能である場合(415条2項1号)
②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(415条2項2号)
③契約が解除されたとき(415条2項3号前段)
④債務の不履行による契約の解除権が発生したとき(415条2項3号後段)
です。
(1)原始的不能でも填補賠償責任が認められることに!
旧法下では、原始的不能の場合(契約成立時に、契約の目的物がすでに全部滅失。例えば、東京で家の売買契約を結んだが、その前日に軽井沢にある別荘が焼失)は、契約無効でした。
しかし、新法では、契約が原始的に不能である場合にも、
① 債務の履行が不能な場合により損害賠償請求が認められます。
(2)債務の履行拒絶の意思の表明がなされた場合の填補賠償
② 債務の履行拒絶の意思の表明は、終局的・確定的に履行の拒絶がなされたときに限られます。
履行不能の場合と同様に扱うことが合理的であると考えられるからです。交渉の途中で履行の拒絶の発言があったとしても、それが終局的・確定的なものかどうかを見極めなければなりません。
(3)契約が解除された場合の填補賠償
③ 契約が解除された場合の填補賠償は、債権者による債務不履行解除の場合に限られません。
合意解除の場合でも、415条1項の他の要件も満たす場合は認められます。
(4)契約は解除されていないが解除権が発生した場合の填補賠償
④ 債務不履行による契約解除権が発生した場合、契約の解除をしなくても填補賠償を認めています。法定解除に値する債務の不履行があった場合、形式的に解除を要求することなく填補賠償を認める趣旨です。
(5)填補賠償に関する経過措置
新法施行日(2020年4月1日)より前に債務が生じた場合の債務不履行責任等では、新法415条の規定にかかわらず、なお従前の例(旧法)によります(附則17条1項)。
施行日以後に債務が生じた場合であっても、その原因である法律行為(例えば売買契約など)が施行日より前にされたときも旧法が適用されます(附則17条1項括弧書き)。
(出典:法務省 説明資料、日本弁護士連合会発行 自由と正義)