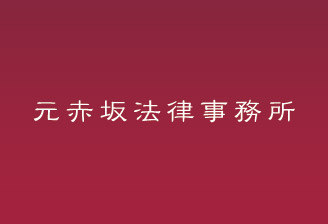

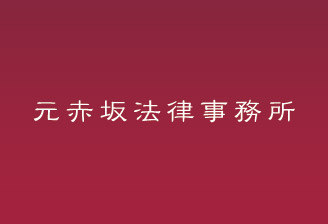


2019年6月現在
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、1896年の民法制定以来、実に約120年ぶりの大改正となりました。この改正は、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応と、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から、実務で通用している基本的なルールを適切に明文化した(条文に書いた)といわれています。
一部の規定を除き、改正債権法は、2020年4月1日から施行(実際に法律が使われること)されます。
なお、文中では、改正前の法律を旧法、改正後の法律を改正法または新法と称しています。文中の条文は、特に断りの無い限り、改正後の条文番号を掲載しています。
契約等に関わる主な改正事項
意思能力制度の明文化(3条の2、121条の2第3項)、意思表示、代理人の行為能力(102条、13条1項10号、120条1項)、消滅時効、法定利率、保証、債権譲渡、約款(定型約款)に関する規定の新設、債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化、契約解除の要件、売主の担保責任、原始的不能の場合の損害賠償規定の新設、債務者の責任財産の保全のための制度(債権者代位権、詐害行為取消権)、連帯債務、債務引受、相殺禁止、弁済(第三者弁済)、契約に関する基本原則の明記、契約の成立、危険負担、消費貸借、 賃貸借、 請負、 寄託というように、多岐にわたっています。
契約は、意思表示の合致(例えば、売ります、買いますという意思表示がぴったり合うこと)で成立します。その意思表示に問題がある場合として、民法は、①心裡留保(例えば、本当は買う気が無いのに、冗談で買うということ)、②通謀虚偽表示(強制執行を免れるため、仮装の売買契約を結ぶ)、③詐欺(だまされた)、④錯誤(勘違いした)、⑤強迫(脅された)の5つのパターンを用意しています。改正法は、心裡留保の場合の、善意の第三者保護規定を新設し(93条2項)、また、第三者による詐欺の場合の相手方の保護要件を見直しました(96条2項)が、最も重要な改正は、錯誤です(95条)。
錯誤(間違い、不一致、勘違い)について
「錯誤」とは、例えば、賃貸マンションの建築請負契約や賃貸マンションの売買契約を締結したものの、後で、実は当該建物が地震や火災に弱いことが発覚した場合等、契約内容又は契約の動機に重大な勘違いがあった場合に、一定の要件の下で、救済を認める制度です。
(1)錯誤の要件の明確化
錯誤は、改正前の条文の文言が「法律行為の要素に錯誤」とわかりづらく、判例の解釈に委ねられていたため、
① 「意思表示が錯誤に基づくもので」あること、
② 「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」こと、
③ 動機の錯誤については、動機である「事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて」いることと、
従来の判例で認められていた要件を明確化しました。
動機の錯誤とは、なぜそれを買おうと思ったかという動機について勘違いがあったことを言います。
たとえば、新駅ができると報道され、いずれ土地が値上がりするだろうと思って土地を買うことにしたが、実際は、新駅ができなかったとか、今なら税金が安くなると聞いて土地を買うことにしたが、実際は税金が安くならなかったなどがこれにあたります。
動機の錯誤の場合、たとえば、契約時に、相手方に、「新駅ができるから土地が値上がりするだろうと思って土地を買うことにしました。」と動機を表示しておくことが重要になります。
(2)契約等の無効から契約等の取消しに
改正前は、誰に対しても何時までも契約の無効を主張できる「無効」でしたが、「取消し」(一応有効、所定期間内に契約の取消の意思表示をして遡って契約が無効となる)に変更されました。
詐欺の被害者が取消しを主張できる期間が、「追認できるときから5年」なのに対して、錯誤無効の主張がいつまでもできるのでは、あまりにも両者のバランスを欠くことから、「取消し」に変更されたのです。
(3)改正法により、勘違いした人の救済が弱くなったといえます。
改正前の民法では、期間制限だけではなく、錯誤について善意無過失の第三者(錯誤についての事情を知らず落ち度が無い人)よりも、勘違いした本人を手厚く保護していました。
例えば、Aさんが勘違いをしてBさんに売却した賃貸マンションを、Aさんが錯誤無効を主張する前に、Bさんが善意無過失のCさんに譲渡し、Cさんが登記を備えたという事例で考えてみましょう。
改正前は、Aさんが錯誤無効を主張すると、不動産をAさんに戻すことができました。改正前は、Cさん(善意の第三者)を保護する規定がなかったからです。
しかし、今回の改正で、「・・錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」(95条4項)と規定されたので、今後は、前掲の事例でAさんが錯誤による取消しをしても、Aさんは善意無過失のCさんに対抗(自分の権利を主張すること)ができなくなります。錯誤による取消を認められる範囲が狭まるからです。
(4)不動産売買契約の調印はこれまで以上に慎重に!
今までのように、億単位の不動産売買をする際、簡単な売買契約書を作り、気軽に調印するのは極めて危険です。
錯誤による取消を認められる範囲が狭まるからです。
勘違いの種はどこにでもありますので、不動産売買契約を締結するに先立ち、印鑑を押す前に、専門家に依頼し、契約書のチェックはもちろんのこと、権利関係、土地の評価、土地の状況等を慎重に調査し、契約時に相手方にどのようなことを伝えておくと良いかなどについて相談をしておく必要があります。
1. 保証契約とは、
主債務者(借金をした張本人)が債務の支払をしない場合に、主債務者に代わって支払をすべき義務を負うことを約束する契約のことです。
(1)通常の保証契約
住宅ローンの保証など、契約時に、特定している債務の保証を、通常の保証といいます。
(2)根保証契約
これに対して、例えば、マンションやアパートの賃借人の債務を親族や知人の方が保証する場合、A社の社長が、B社との間で、A社がB社に対して負担する全ての債務をまとめて保証する場合など、保証人となる時には現実にどれだけの金額の債務を保証するのか分からないことがあります。
このように、将来発生する不特定の債務の保証を、根保証といいます。根保証契約では、保証人になる際には、主債務の金額がわからないため、保証人は、予想外の債務を負うことになりかねませんでした。
そこで、法は、今回の改正も含め、以下のように規定しています。
保証は、経済取引関係できわめて重要ですので、手続面も含め、ある程度詳しく説明していきます。
2. 主債務に貸金が含まれる根保証契約
主債務に貸金等債務が含まれる根保証契約(個人貸金等根保証)については、2005年の民法改正で今回の改正よりもさらに厳しい規制がすでにされており(貸金等債務に関する包括根保証の禁止)、この規制は、今回の改正後も変わりません。
3. 個人の根保証に関する改正
今回の改正では、「個人貸金等根保証」の規律を、全く同じ規律ではないですが、あらゆる債務に関する個人根保証一般に拡張しました。具体的には、
(1)極度額(上限額)の定めの無い個人の根保証契約は、無効となります(465条の2)。
この極度額は、例えば「300万円」というように明確に、書面等により当事者間の合意で定める必要があります。保証人は、極度額の範囲で支払の責任を負います。
例えば、「建物賃貸借契約」で、大家さんが賃料不払いや原状回復債務に備え根保証契約にするとします。この際、必ず極度額を定めておかなければなりません。極度額の定めずに根保証契約をしてしまうと、せっかく結んだ保証契約が無効となり、保証人に支払を求めることができなくなるので注意が必要です。
(2)一定の事由が生じた場合の元本の確定(その後に発生した債務は、根保証の対象になりません)。
個人根保証契約(例えば賃貸借契約や継続的売買契約等)について、保証人(主債務者は除外されています)が破産したときや、主債務者または保証人が死亡したとき、その後に発生する主債務は、根保証の対象外です(465条の4第1項)。
4. 事業に係わる債務についての個人保証の特則
改正民法は、事業に係わる債務についての個人保証の特則を設けました。
一般的に個人保証は、断り切れず情で締結されることが多く、保証人となる個人は、リスクを甘くみがちです。また、事業に係わる貸金等債務は、保証人の負担が予想外に重くなる可能性があるため、事業に係わる債務(例えば事業用融資)の個人保証について特則を設けています。
(1)公正証書による保証意思の確認
「事業のために負担した貸し金等債務に係わる個人保証」については、保証契約を結ぶ前、保証契約の締結の日前1箇月以内に作成された、公正証書による保証意思の確認措置を執らない限り、保証契約は無効となります(465条の6~9)。
なお、この意思確認手続は、主債務者の事業と関係の深い、いわゆる「経営者保証」の場合、不要とされています(465条の9)。業務執行の決定に関与できる人は、情による保証の面が少なく、業務執行の決定に必要な情報を入手することもできるし、保証が経営の規律付けに寄与する面があるからです。
主債務者の事業と関係の深い人は、明文で列挙されおり、①主債務者が法人である場合、法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等、②主債務者が個人である場合、共同事業者、主債務者の事業に、現に従事している主債務者の配偶者などがこれにあたります。
法改正の段階で、個人事業主の配偶者(共同事業者ではない者)、名目取締役は、経営者に含めるべきではないという議論がありました。
意思確認手続が必要かどうかについて疑義がある場合、確認手続にかかる費用は、保証額からすれば些少ですので、債権者は、念のため意思確認手続をとっておくとよいでしょう。
意思確認の方法は、方式が厳格に法定されています(465条の6第2項)。
具体的には、保証人候補者が、公証人に対し、主債務・保証債務の内容や保証債務を履行する意思があること等を口授し、公証人に筆記してもらい、保証人候補者がその内容を確認した上で署名押印します。口授内容等については、もう少し詳細な定めがありますので、手続き前に条文を一度ご確認ください。なお、公証人は、公証役場にいます。
(2)契約締結時の情報提供義務と義務違反の効果
主債務者は、事業のために負担する債務(貸金債務に限らず、賃貸借や売買による債務も含まれます)について他人に個人保証を委託する場合、その人が保証人になって良いかかどうかの判断に資する情報として、
①主債務者の財産や収支の状況、
②主債務以外の債務の金額や履行状況等に関する情報を、正しく保証人候補者に提供しなければならない義務を負うことになりました(465条の10第1項)。
主債務者がこの義務に違反して、情報を提供せず、あるいは事実と異なる情報を提供したために委託を受けた保証人候補者が誤認をし、それによって保証契約の申込み、または承諾の意思表示をした場合、主債務者が情報の提供せず、または事実と異なる情報を提供したことを債権者が知ることができたときは、保証人は保証契約の取消ができます(465条の10第2項)。
情報提供義務を負っているのは主債務者ですが、債権者は、主債務者が正しい情報を提供したかどうかを確認しないと、保証契約の取消しというリスクを負うことになります。債権者は、主債務者が提供した情報内容と保証人候補者が提供された情報内容に齟齬がないかを確認できる方策を講じておくことが必要となります。
5. 契約締結後の情報提供義務
(1)債権者は、主債務者の履行状況に関する情報提供義務を負います(委託を受けた保証一般)。
主債務者の委託を受けて保証人(法人を含みます)になった場合、保証人が債権者に主債務の履行状況等について問い合わせをしたとき、債権者は遅滞なく、これらの情報を提供する義務を負います(458条の2)。主債務の履行状況について、保証人は密接な利害をもつため問い合わせの必要があるからです。
提供義務を負う情報内容は、主債務の元本、利息 及び違約金等に関する ① 不履行の有無(弁済を怠っているかどうか) ② 残額 ③ 残額のうち弁済期が到来しているものの額についてです。
(2)債権者は、債務者が期限の利益を喪失した場合、情報提供義務を負います(個人保証一般)
例えば、債務者が分割金の支払を遅滞して結果、一括払の義務を負うことを「期限の利益の喪失」といいます。
主債務者が期限の利益を喪失すると、遅延損害金の額が大きく膨らむ可能性があり、保証人が多額の支払いを求められる可能性もあります、逆に、保証人が主債務者の期限の利益喪失を早く知ることができれば立替払等で対策をとることもできます。そこで、本条が新設されました(458条の3)。
保証人が個人である場合、債権者は、主債務者が期限の利益を喪失したことを知った時から2か月以内に、その旨を保証人に通知しなければなりません。
2か月以内の通知を怠ると、債権者は、個人保証人に対し、主債務者が期限の利益を喪失した時から通知をするまでに生じた遅延損害金について請求できなくなります(もっとも、主債務者にはこの間の遅延損害金についても支払義務があります)。
例えば、債権者が期限の利益喪失を知ったときから2か月以内に通知せず、保証人に通知をしたのが期限の利益喪失後3ヶ月だった場合、3か月分の遅延損害金の請求を保証人にすることはできなくなります。
6. 連帯債務に関する見直し
改正法では、連帯債務の絶対的効力事由が削減されました(441条)。
①連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じなくなりました。 ②連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成も、他の連帯債務者に効力が生じません。
連帯保証人についても、同様の改正がなされ、保証人に対する履行の請求は、主債務者に対して効力を生じません(458条、441条)。したがって、債権者が連絡保証人にのみ履行の請求を行った場合、主債務者には原則としてその効力が及ばないので、時効管理の関係で債権者は注意が必要です。
具体的には、連帯保証人にだけ履行の請求をするのではなく、主債務者にも別途、履行の請求をしておく必要があります。
主債務者の居場所が不明でも履行の請求をしたと同様の結果が生じる手続はございますので、その様な場合は、弁護士にご相談ください。
これまで保証に関する改正点を見て参りました。
情報提供義務や通知義務の新設により、保証人候補者は、保証人になって良いかどうかの見極めがしやすくなりましたし、保証人は、債権者への問い合わせにより主債務者の遅延損害金が膨らむ前に対策することができるようになりました。また、保証契約が無効になる場合も新設されています。
これらは、逆に言うと、「債権者が債権を回収するためのハードルがかなり高くなった」ことを意味します。債権者は勤勉に債権の管理や通知、対処をしていないと、債権の回収ができないおそれが高まりましたので、保証に関しては、どの段階でどのような手続がいつまでに必要かを是非、保証契約を締結する前にご確認ください。
改正のポイントは、
①法定利率は、2020年4月1日の改正法施行時に法定利率が3%となり、その後三年ごとに利率の見直しを行う緩やかな変動制をとること、②商事法定利率規定等の廃止です。
法定利率の変動
(1)法定利率は、商事法定利率の定め(商法514条)が廃止され(整備法3条1項)、民事、商事の区別がなくなりました。
(2)市中金利等との乖離が大きいとの批判があった法定利率(民事法定利率5%)は、固定制から変動制に変わりました。もっとも常時、法定利率が変動すると債権管理等の負担が大きくなります。そこで、新法は改正法施行時(2020年4月1日)の法定利率を年3%とし(404条2項)、その後三年ごとに見直しを行うという緩やかな変動制を採用しました(404条3項)。
従って、契約の機会の多い方は、2023年4月1日以降は、念のため、契約の都度、インターネット等で法定利率の確認をするとよいでしょう。
なお、法定利率は変動しますが、適用される法定利率は、特段の意思表示の無い限り、その利息が生じた最初の時点における法定利率に固定されるので(404条1項)、注意が必要です。
例えば、利息つきであることだけを定め利率を決めずに貸した金銭の利率は金銭を交付した日(589条2項)の利率に固定され、その後に法定利率が変動しても変動しません。金銭債務の不履行による遅延損害金については、債務者が遅滞の責を負った最初の時点における法定利率を使用することになります(419条1項)。
法定利率の経過措置は下記のとおりです。
(1)2020年4月1日より前に利息が生じた場合、その利息が生じる債権に係わる法定利率は、
旧法によります(附則15条1項)。
(2)2020年4月1日より前に債務者が履行遅滞の責任を負った場合の遅延損害金の法定利率は、
旧法によります(附則17条3項)。
中間利息控除について
中間利息控除とは、交通事故などの損害賠償において死亡被害者の逸失利益を算定するに当たり、将来得たであろう収入から運用益を控除することです。
(1)中間利息控除の問題とは、例えば交通事故の損害賠償請求において、死亡被害者の逸失利益を算定するに当たり、その被害者が将来得たであろう収入から、運用益(将来もらうお金を一括で銀行に預けた場合の利息分)を控除されます。旧法では中間利息として5%控除されていましたが、超低金利時代の昨今、5%は控除しすぎで被害者保護に著しく欠けると強い批判がありました。
(2)新法では、中間利息を控除するときは、その損害賠償請求権が生じた時点における法定利率によることとされました(417条の21項)。これにより、法定利率と異なる利率による中間利息控除は認められないことが明文化されました。
(3)中間利息控除は、法定利率によるので、交通事故の損害賠償請求では、事故発生時の法定利率を調べて、その法定利率で中間利息を控除することになります。
事故時の法定利率に連動するということは、物価が上昇し、法定利息が上昇している状況下で事故が起これば、被害者が得る将来の運用益を超えた、多額の中間利息が控除される事態が起こり得るということにもなります。
(4)中間利息控除の経過規定
2020年4月1日より前に損害賠償請求権が生じている場合は旧法、同年4月1日以降に生じた損害賠償請求権については、新法によります(附則17条2項)。
消滅時効とは、賃料債権等の法律上の権利を一定期間行使しないでいると、一定の要件の下、権利が消えてしまうことを認める制度です。
消滅時効の主な改正点は次のとおりです。
①援用権者(時効の利益を主張する者)の明確化、②職業別短期消滅時効及び商事消滅時効の廃止し、時効期間と起算点をシンプルに統一化 ③生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間を長期化する特則の新設 不法行為債権に関する長期20年の期間制限を除斥期間とする解釈(判例)の見直し ④時効の完成を阻止するための手段(時効の中断・停止)の見直しなど
1. 消滅時効の援用権者(時効の利益を主張する者)の明確化
消滅時効の援用権者として、当事者のほか、保証人、物上保証人(他人の債務のために担保を提供した人)、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれることを明示しました。
2. 職業別短期消滅時効の廃止
職業別短期消滅時効は複雑で合理性があるか疑問視され廃止されました(旧法170条~174条削除)。
また、商事消滅時効5年は、それが適用される債権とされない債権を合理的に区別できるかという批判を受け廃止されました(旧商法522条削除)。
(1)新法は、債権は、権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年という時効期間は維持しつつ、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年という時効期間を追加して、 いずれか早い方の経過によって消滅時効が完成するとしました(166条1項1号、2号)。
なお、通常、権利発生時にその債権の権利行使の可能性を認識しているのがふつうなので、主観的起算点と客観的起算点とは基本的には一致することが多いといえます。
3. 人身侵害による損害賠償請求権における消滅時効の期間の延長
(1)人の生命・身体という法益の重要性から、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間について、長期化させる特則が新設されました(167条、724条の2)。
これにより、
①債務不履行に基づく損害賠償請求権は、原則として権利を行使することができることを知った時から5年、 権利を行使することができる時から10年
②不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として 損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時(権利を行使すること ができる時)から20年
③生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、①、②の特則として167条、724条の2が新設され、
知った時から5年、 権利を行使することができる時から20年となり、不法行為と債務不履行の消滅時効期間が一致しました。
(2)従来の判例理論では、旧法724条後段に定める20年は除斥期間とされていましたが、新法では、不法行為債権全般について、不法行為債権に関する長期20年の制限期間が時効期間であることが明記されました(724条2号)。
(3)製造物責任法についても、人身侵害の場合の損害賠償請求権の消滅時効が、従来、損害及び加害者を知った時から「3年」から「5年」に変更となります(製造物責任法5条2項)。
4. 時効の「中断」から時効の「更新」に
時効障害事由は、旧法の「中断」(これまで積み重ねてきた時間がゼロに戻り、新たな時効のカウントダウンがスタートすること)・「停止」(時効の完成が単にストップしているだけ。積み重ねの時間はゼロには戻らない)から、新法では「更新」「完成猶予」という名称に変わりました。
これは、旧法の「中断」という概念が複雑で分かりづらい、裁判上の催告に関する判例法理を明文化すべきではないかとの批判を受けてのものです。
5. 当事者の協議による時効完成猶予制度の新設(151条)
せっかく当事者が裁判所を介さずに紛争の解決に向けて協議、交渉中であるのに、時効完成直前になると、時効の完成を阻止するため、当事者が望まない訴訟を提起しなければならないということがたびたびあります。これでは、紛争解決の柔軟性や当事者の意思を損なうので、新たな完成猶予事由を設けるべきではという声を踏まえて新設された制度です。
当事者間で権利についての協議を行う旨の合意が書面または電磁的記録によってされた場合には、時効の完成が猶予されます(151条)。
その他
天災等避けることのできない事変が生じた場合は、時効の完成猶予の期間(その障害が消滅した後の猶予期間)が、現在の2週間から3か月へ伸張されました(161条)。
契約を締結したのに債務者が契約上の義務を果たさない場合について、今回の債権改正法では、契約責任の現代化という要請に基づき、①債務不履行に基づく損害賠償の帰責事由の明確化(変容) ②契約解除の要件の見直し(債務者の帰責事由不要) ③催告による解除の制限と無催告解除の要件の明文化 ④危険負担の見直し(履行拒絶権への移行) ⑤売買契約の担保責任の全体的な見直しがなされました。
この部分は、大変難しい言葉が出てきて、また、違いがよくわからないような専門的な話も出てくる分野です。契約で、なにかトラブルが生じた場合に使う規定ですので、改正の指摘にとどめ、トラブルが生じたときは、早めに弁護士にご相談されることをお薦めいたします。
1. 債務不履行に基づく損害賠償の帰責事由の明確化について
(1)債務不履行の要件としての債務者の帰責事由
債務不履行の要件としての債務者の帰責事由債務不履行による損害賠償は、債務者に帰責事由(責めに帰すべき事由)がないときは免責されます。
このことは履行不能の条文にのみ規定されていますが(旧法415条後段)、同条前段(履行遅滞、その他)にも共通のルールと解されていることに争いはなく、条文と解釈に齟齬が生じていました。
また、旧法下では、帰責事由を「債務者の故意または過失及び信義則上それと同視しうる事由」と解するのが通説でした。
(2)改正法による債務者の帰責事由の明文化
改正法は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と明記しました(415条1項)。その帰責事由は、具体的には、当事者の合意した内容、目的、契約締結の経緯など一切の事情を考慮し、取引通念をも勘案して総合的に判断されます。
2. 債務の履行に代わる損害賠償(填補賠償)について
新法は、填補賠償が認められる場合を明確にしました。
債務の履行に代わる損害賠償が認められるのは、
①債務の履行が不能である場合(415条2項1号)
②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(415条2項2号)
③契約が解除されたとき(415条2項3号前段)
④債務の不履行による契約の解除権が発生したとき(415条2項3号後段)
です。
(1)原始的不能でも填補賠償責任が認められることに!
旧法下では、原始的不能の場合(契約成立時に、契約の目的物がすでに全部滅失。例えば、東京で家の売買契約を結んだが、その前日に軽井沢にある別荘が焼失)は、契約無効でした。
しかし、新法では、契約が原始的に不能である場合にも、
① 債務の履行が不能な場合により損害賠償請求が認められます。
(2)債務の履行拒絶の意思の表明がなされた場合の填補賠償
② 債務の履行拒絶の意思の表明は、終局的・確定的に履行の拒絶がなされたときに限られます。
履行不能の場合と同様に扱うことが合理的であると考えられるからです。交渉の途中で履行の拒絶の発言があったとしても、それが終局的・確定的なものかどうかを見極めなければなりません。
(3)契約が解除された場合の填補賠償
③ 契約が解除された場合の填補賠償は、債権者による債務不履行解除の場合に限られません。
合意解除の場合でも、415条1項の他の要件も満たす場合は認められます。
(4)契約は解除されていないが解除権が発生した場合の填補賠償
④ 債務不履行による契約解除権が発生した場合、契約の解除をしなくても填補賠償を認めています。法定解除に値する債務の不履行があった場合、形式的に解除を要求することなく填補賠償を認める趣旨です。
(5)填補賠償に関する経過措置
新法施行日(2020年4月1日)より前に債務が生じた場合の債務不履行責任等では、新法415条の規定にかかわらず、なお従前の例(旧法)によります(附則17条1項)。
施行日以後に債務が生じた場合であっても、その原因である法律行為(例えば売買契約など)が施行日より前にされたときも旧法が適用されます(附則17条1項括弧書き)。
1. 契約解除の要件として債務者の帰責事由(責めに帰すべき事由)は不要に
(1)旧法では解除の要件として債務者の帰責性(法的な責任があること)が必要
旧法543条ただし書きは、履行不能について、債務者に帰責事由がない場合には解除が認められないと定めていました。そして、通説は、解除一般について帰責事由が必要であると解していました。例えば、買主A売主B間でクーラーの売買契約を結んだところ、売主Bの倉庫が第三者の放火で全焼し、納期を過ぎても復旧の見込みがたたないので、Aは、Cからクーラーを調達するためにAB間の契約の解除をしたいと思っていても、B(債務者)に帰責性(法的な責任)が無いので契約の解除ができませんでした。
(2)解除の要件として債務者の帰責性が不要に
改正法では、債務不履行による解除一般について、債務者の帰責事由が無くても解除を可能にしました(541条、542条)。つまり、上記の例でのA(債権者)は、契約の解除ができるようになりました。
ただし、不履行で債権者に帰責事由がある場合は、解除を認めるのは不公平になるので、解除はできません(543条)。
2. 契約解除は債権者を反対債務から解放する手段
債務者に帰責事由がある場合に限り解除を認めた旧法は、解除も損害賠償請求と同じく債務者の責任を追及手段であると位置づけていました。
しかし、新法は解除に債務者の帰責事由を不要としたため、解除は、債務者の責任を追及するものではなく、債権者を自らの債務から解放する手段ととらえていると理解できます。
前述の事例でいうと、A(債権者)がAB間の契約を解除するのは、B(債務者)への責任追及では無く、Aが負う代金支払い債務を消滅させるためということになります。
3. 契約解除の改正について資産活用に関する実益
帰責事由の有無の判断は難しいので、帰責事由無く解除ができるという今回の変更は、実用的であると考えます。
例えば、注文した建物建築工事が遅遅として進まない場合や建築工事が履行不能になった場合、「請負人の帰責性を問わず」、請負契約を解除し、
より良い建築事業者と建築請負工事を締結することが可能になります。
4. 催告による解除が制限される場合
(1)問題の所在として旧法の条文
問題の所在として、旧法の541条(履行遅滞等による解除権)の文言では、あらゆる債務不履行について催告さえすれば契約の解除が認められるようにも読めました。
しかし、 判例は、付随的な債務の不履行や、不履行の程度が必ずしも重要でない場合については、催告をしても解除が認められないとしていました。
(2)新法は明文で「軽微」な債務不履行では解除不可と規定
新法では、催告による解除の要件に関して、判例を踏まえ、債務の不履行が「契約及び取引通念に照らして軽微であるとき」は催告による解除が認められないと明文化しました(541条ただし書き)。
「軽微」というのは、不履行が数量的に少なかったり、付随的な債務の不履行にすぎない場合をいいます。
また、不履行によって契約目的の達成が不可能とまではいえなくても、契約目的の達成に重大な影響を与えるような場合は、催告による解除は認められます。
(3)真に「軽微」な不履行なら問題はありませんが・・・
ただ「軽微」か否かの判断は、裁判官の判断によってまちまちとなる場合も多く、建物建築では、注文者にとって重要な手抜き工事があったとしても、裁判上は「軽微」な不履行であると認定され、請負契約の解除ができない、ということになりかねません。その意味でも、建築事業者は、慎重に選ぶ必要性があるといえます。
5. 解除に関するその他の改正
(1)新法は、無催告解除ができる場合を明確にしました(542条1項1号から5号)
(2)新法は、解除に帰責事由を不要としたことにより、解除をする場面が増えることもあり、催告によらない一部解除についても明文化しました(542条2項)。
(3)債務の不履行が債権者の帰責事由による場合の契約解除の否定(543条)
帰責事由のある債権者についてまで、解除による契約関係からの離脱を認めるのは適当ではないからです。
6. 解除に関する改正の経過規定
施行日(2020年4月1日)より前に契約が締結された場合の契約解除については、新法541条から543条まで、545条3項及び548条の規定にかかわらず、旧法が適用となります(附則32条)。
(1)危険負担
危険負担とは、双務契約(売買契約の売主の目的物移転義務・買主の代金支払い義務のように、当事者双方が対価関係を有する債務を負う契約)の一方の債務(売主の目的物移転義務)が履行不能により消滅した場合に、他方の債務(例えば買主の代金支払い義務)も消滅するか、それとも消滅しないか、という問題です。
(2)危険負担の具体例
住宅の売買契約成立後、引渡日前に大地震で家が崩壊してしまった場合、債権者が負っていた家の引渡「債務」は、履行不能により「消滅」します。
それにも拘わらず、買主の代金支払い「債務」は、なお「存続する」のか、それとも「消滅」するのか、それが旧法下の危険負担の話でした。
(3)危険負担に関する旧法の扱い
旧法では、一方の債務が履行不能により消滅した場合、他方の債務も消滅する(債務者主義、旧536条1項)、とされていました(物の引渡債務が消えたので、代金支払い債務も消えるのが公平)。
但し、旧法下では、例外として債権者主義(旧534条1項など)が規定されており、先ほどの家の崩壊の事例では、「売主の債務は消えたのに代金債務は消滅しない」とされていました。
(4)旧法の扱いに対する批判
この結論に対し、売主の家引渡債務は消滅したにも拘わらず、買主の代金支払い義務は存続し、買主は家の代金を支払わなければならないとするのは、不公平であると言う強い批判がありました。
(5)危険負担に関する改正内容
① まず、新法では、批判の強かった旧534条、旧535条は削除されました。
② 次に、旧536条1項の文言は、債務者は「反対給付を受ける権利を有しない」と定められ、当然に、売主が有する代金支払いを受ける権利は消滅するとの規律でした。
これに対して新法536条1項は、「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」と定めています。これは、債権者(買主は)、売主からの代金支払い請求を拒むことができるということなので、反対給付債務(買主の代金支払債務)は、当然には消滅しないことになりました。
買主が代金支払債務を確定的に消滅させるためには、債務不履行による契約解除をする必要があります。
前述のとおり、債務不履行の契約解除に、債務者の帰責性は不要になったので、買主は売主に帰責事由が無くても契約の解除ができます。
(6)危険負担に関する改正の実益
① 旧法下の「買主の代金支払債務は存続するのか、消滅するのか」という考え方から、新法では、「買主は売主による代金支払請求を拒絶できるのか、できないのか」という話に変わり、
② 債権者(先述例の買主)は、債務者(売主)の義務が履行不能になったことについて、自ら(買主)に責任がない限り、先程の不可抗力で契約目的物(建物)が滅失したようなケースにおいても、反対債務(代金支払い義務)の履行を拒むことができるようになりました。
(7)改正の経過措置
施行日(2020年4月1日)前に締結された契約については、旧法が適用されます(附則30条1項)。
1. 種類物売買と特定物売買
種類物売買とは、例えば、「○○産のMサイズの蜜柑100個の売買」というように一定の種類の目的物を一定数量売買の目的物とする場合を言います。
これに対し、特定物売買とは、「○○に所在する中古住宅一棟を売買の目的とする場合等、売買の当事者が目的物の個性に着目して(言わば世界に一つの物として)売買の目的」とした場合を言います。
2. 旧法の「特定物売主」の担保責任
例えば、特定物である中古住宅一棟を売買契約の目的物としたところ、「売買契約前から目的物に欠陥(原始的瑕疵)があること」が発覚した場合、法律上の特別の責任として、
① 売主は、原則として、瑕疵に相当する金額(瑕疵がないことを想定した売買金額と欠陥がある状態での目的物の差額)の損害賠償義務を負い、
② 買主は、欠陥があることにより契約目的を達することができない場合に、契約の解除をすることができたものの、
③ 特定物売主(中古住宅の売主)は、特約なき限り、欠陥の修補義務を負わず、上記差額以上の損害賠償義務を負わない、とされていました。
3. 改正の理由
旧法の下では、売主の責任は、種類物売買と特定物売買で規律が異なる等、相当難解な制度になっていました。
そこで、買主が受けられる救済につき、分かりやすく合理的なルールを明示するという改正趣旨により、改正法は、以下のようになりました。
これは、反面、中古住宅の売主等特定物売主の責任が厳格になることを意味します。
4. 売主の責任は改正法で厳格に?
(1)シンプルになった売主の責任
特定物売買と種類物売買を区別することなく、
① 売主は「売買契約の内容に適合した目的物」を引き渡す義務を負い、
② 買主は、売主に対し、売主と買主のいずれに帰責事由があるかに応じて損害賠償請求、解除のほか(564条)、修補請求(目的物が契約内容に適合するまでの修補請求)や、代替物・不足分の引渡し請求等、履行の追完請求をすることができるようになり(562条1項本文)、代金減額請求もできるようになりました(563条1項)。
(2)売主の契約不適合責任(売主の修補義務が先行)
新法563条1項は、目的物の性能が契約内容に適合しない場合、買主が相当の期間(目的物の性能が契約内容に適合するまで)を定め履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完(修補・代物の交付)がないとき、買主は代金減額請求ができると定めています。
従って、基本として履行の追完(目的物の修補、代替物または不足分の引渡し)が先行し、売主が追完(修補等)をしない場合に代金減額請求ができることを前提にしていることに注意が必要です。
5. 改正民法売主の担保責任(契約不適合責任)のまとめ
帰責事由の所在と救済方法を簡単にまとめると、以下のようになります。
① 契約内容の不適合(目的物の欠陥等)につき、買主に帰責事由があるとき、買主は、損害賠償、解除、追完請求、代金減額請求のいずれもすることはできません。
② 契約内容の不適合(目的物の欠陥等)につき、売主に帰責事由があるとき、買主は、追完請求(目的物が契約内容に適合するまでの修補請求・契約内容に適合する代物請求)、損害賠償(契約内容に達するまでの修補に代わる損害賠償)、解除、代金減額請求の4つの請求をすることができます。
③ 契約内容の不適合(目的物の欠陥等)につき、売主買主の双方に帰責事由がないとき、損害賠償請求をすることはできませんが、それ以外の解除、追完(修補・代物等)請求、代金減額請求はできます。
6. 売主の契約不適合責任の期間制限
① 買主は、上記請求をするためには、引き渡された商品が契約に適合していないことを知ってから1年以内に、売主にその旨を「通知」しなければなりません(566条本文)。
② この通知は、不適合の事実の通知のみで足りる(訴えの提起までは不要)とされていますので、旧法下よりも当初の買主の負担が軽減されています。
③ 566条ただし書きは、売主が内容不適合につき悪意または重過失の場合、例外的に一般の消滅時効の規定が適用されるとしています。
7. 経過措置
施行日(2020年4月1日)前に締結された売買契約及びこれに付随する買戻しその他の特約については、旧法が適用されます。(附則34条1項)。
買戻し(579条)
旧法下では、買戻し特約により買戻しをするには、「代金と契約費用を返還」と、金額の範囲が定められており、この規定は強行規定(特約で法と違った定めをしても、特約の効力を生じない規定)と解されていました。
買戻しを利用しやすくするため、新法は金額の範囲を当事者で任意に定めることができるようにしました(579条)。
賃貸借契約とは、賃料を支払って有料で物の貸し借りをする契約です。これに対し、お金を払わず無料で物の貸し借りをする契約を使用貸借契約といいます。
改正債権法の賃貸借の改正のポイントを、順に確認していきます。
若干の新設事項はありますが、多くは、これまで判例法理や一般的な理解に頼ってきた部分を明文化した(条文に書いた)ものです。
1. 契約終了時の目的物返還義務の明示(601条)
賃借人は、賃貸借契約が終了したときに目的物を返還しなければなりません。
しかし、旧法は、返還義務を明示的に規定していなかったため、改正法では、賃貸借の冒頭規定に、「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」と規定し、明文化しました。
2. 民法の賃貸借の存続期間が最長20年から50年へ
旧法では、民法上の賃貸借の最長期間は、20年でした。
しかし、ゴルフ場の敷地の賃貸借等、長期化を求める需要がある一方、他方で、上限を設定しないと、目的物の所有者に過度の負担となりえます。
そこで、新法では最長50年としました(604条1項)。更新についても更新の時から最長50年です。(同条2項)。なお、借地借家法や農地法が適用される賃貸借については、今般の改正による影響は基本的にありません。
⒊ 賃貸の目的物の修繕に関する規定の見直し
賃貸物件に備え付けのエアコンが故障したり、借りている建物の天井から雨漏りがしたりなど、賃借物について修繕が必要なことがあります。
旧法では、賃貸人が賃貸物の修繕義務を負っているとのみ規定されていました。しかし、賃借人の帰責事由(責任を負わなければならない理由)で修繕が必要になったときにまで、全て賃貸人が修繕義務を負うというのは不公平ですし、また、賃借人に帰責性がない故障にもかかわらず、賃貸人が修繕になかなか応じないとき、賃借人が困ります。
そこで、改正法は、公平性の観点から、賃借人の帰責事由により修繕が必要となった場合には、賃貸人は修繕義務を免れることとしました(606条1項ただし書き)。
また、賃借物の修繕が必要な場合で、
① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず相当期間必要な修繕しないとき、
または
② 急迫の事情があるとき
は、賃借人が修繕する権限を認めました(607条の2)。
4. 賃借人の責によらない賃借物の一部滅失等による賃料減額規定の見直し
賃借物の一部が滅失した場合、旧法では、賃借人が賃料の減額請求をできる旨、規定していました。
しかし、改正法は、賃借人による請求を待たずに、当然に賃料が減額されるとしています。
さらに、賃借物の一部が滅失した場合だけでなく、その他の事由により賃借物の一部の使用が不能となった場合にも賃料が減額される旨規定しています(611条1項)。つまり、減額に賃借人の請求が不要になり、減額事由が拡大することになりました。
5. 不動産の賃貸人の地位の移転及び留保制度
(賃貸目的物が譲渡されたような場合に、問題になります)
例えば、AがBに賃貸中の不動産を、Aが、第三者Cに売った場合、AB間の賃貸借契約はどのようになるのか、具体的には、Bは、誰に賃料を支払い、また、CはBに賃料請求ができるのか等の問題です。
改正前は、判例理論により解決をしていましたが、改正法ではこの判例のルールを明文化しました。また、留保の制度が新設されました。
前提知識として、不動産賃貸借の対抗要件(当事者以外の第三者に、自分が権利者だと主張する条件)について確認しておきますと、
民法上は、不動産の賃借権の登記であり、借地借家法上は、土地の場合、借地上の建物の登記、建物の場合、建物の引渡です。
(1)対抗力を備えた不動産賃貸借については、賃貸不動産が譲渡されれば、賃貸人の地位が当然に譲受人に移転することを明記しました(605条の2第1項)。これまでの判例法理を明文化したものです。
賃借人が対抗力を備えていると、不動産の譲受人は、この賃借人を追い出すことはできないので、法律上当然に賃貸人の地位を譲受人に移転させ、新賃貸人にしたのです。上記の事例でいうと、Bが賃借権について対抗要件を備えていれば、Aの賃貸人の地位は、当然にCに移転し、Cが新賃貸人、Bが賃借人となります。
(2)改正法は、(1)の例外として、譲渡当事者間の合意により、賃貸人の地位を譲渡人に留保する制度を新設しました(605条の2第2項前段)。
もともと賃貸していた不動産を、サブリースにする場合等(不動産の所有権は、委託者から受託者に移転)、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する必要があることがあるからです。
賃貸人の地位の留保の要件は、
①譲渡当事者間(AC間)で賃貸人たる地位の留保を合意すること、及び
②譲受人(C)が譲渡人(A)に目的物を賃貸する合意です。
留保により賃貸人と所有者が分離することから、賃借人の不利益を防止するため、②の賃貸の合意を要求しました。
その結果、譲受人(C)が譲渡人(A)に賃貸し、譲渡人(A)と賃借人(B)は、従来からの賃貸借関係を維持することになります(CがAに貸した物を、AがBに貸すという転貸借関係)。
(3)賃貸人の地位を留保した(2)の場合で、譲受人(C)と譲渡人(A)間の賃貸借契約が終了したときは、原則に戻り、賃貸人たる地位が譲渡人(A)から譲受人(C)またはCからの承継人に当然に移転することにしました(605条の2第2項後段)。
賃借人(B)の関与なく賃貸人の地位の留保を認める以上、譲渡人(A)が賃借権を失った場合には、テナントである賃借人(B)が所有者(譲受人CまたはCの承継人)との間で賃借権を主張できるようにするためです。
その他、改正法は、判例法理や従来の一般的な理解を明文化しました。
➀ 賃貸人の地位が法律上当然に移転する場合、新賃貸人(C)が、賃貸人の地位の移転を賃借人(B)に主張する、例えば、賃料の請求や賃料不払いによる明け渡し請求をするには、賃貸目的物に、新賃貸人(C)の所有権移転登記が必要になります(605条の2第3項)。なぜなら、AがCに不動産を譲渡するとき、Bの承諾は不要ですから、Bが知らない間にCが不動産の新所有者になっていることは多々あります。そして、ある日、見知らぬCから、突然賃料を請求されたり、明け渡し請求をされるのではBが驚くので、Cが賃貸人たる地位の移転を主張するには、賃貸目的の不動産の登記を備えなければならないとしたのです。
② 賃貸人の地位が法律上当然に移転する場合、敷金返還債務や費用償還債務を譲受人(C)は、当然に承継します(同条第4項)。Bは差し入れた敷金を、新賃貸人から返還してもらうことになります。
③ 不動産賃貸借においては、たとえ賃借権が対抗力を備えていなくても、目的物の譲渡当事者間の合意のみで(賃借人の承諾不要ということ)賃貸人の地位が移転することを規定しました(605条の3)。
対抗力がない不動産賃借人(B)を譲受人(C)は追い出すことはできますが、AC間で賃貸人の地位の移転を合意することは可能です。Bにも不利益が無いからです。
6. 不動産賃借権に基づく妨害停止の請求等
BがAから賃借している建物が、Cにより不法占拠されたとします。
このような場合、対抗要件を備えた不動産の賃借人は、賃借権に基づき妨害する第三者に対する妨害の停止や返還の請求をすることができます(605条の4)。従来の判例法理や一般的な理解を明文化したものです。
なお、本条の規定は、施行日以前に不動産の賃貸借契約が締結されていた場合でも、その不動産を第三者が妨害・占有したのが施行日以後であれば、適用されるので、是非、知っておかれると良いと思います(附則34条3項)。
7. 賃借人の原状回復義務に関する規定新設
賃貸借契約が終了すると、賃借人は、借りていた物を元の状態に戻したうえで返還しなければなりません。これを原状回復義務といいます。旧法では、賃借人の原状回復義務を直接規定する条項がありませんでした。
新法では、賃借人は,賃借物を受け取った後に生じた損傷について、賃貸借終了時点においてその損傷を原状に復する義務を負うと規定し、義務を明確にしました。また、通常損耗や賃借物の経年変化、賃借人の帰責事由によらない損傷については同義務の対象にならないことも明記しました(621条)。これまでの判例法理や一般的理解を踏まえたものです。
ただし、従来からの重要判例(最高裁平成17年12月16日判決)ですが、特約により、通常損耗についても原状回復義務を賃借人に負わせることはできます。しかし、かかる特約が有効と認められる要件は厳格ですので、賃貸人は、弁護士と相談の上、契約書を工夫し作成することが重要です。
8. 敷金に関する規定の新設
(1)敷金の定義
不動産取引では、さまざまな名称の金銭が授受されることが多いといえます。しかし、従来の民法には、敷金の定義について明文がありませんでした。
そこで、改正法は、従来の判例理論を明文化し、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義しました(622条の2第1項)。
この定義によれば、たとえ保証金名目であっても担保目的であれば敷金のルールに従うことになるので、注意が必要です。
(2)敷金返還義務の発生時期
返還義務の発生時期は、
➀賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき(明渡時説の採用)
または
②賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき
と定められました。
(3)敷金返還のその他のルール
➀賃貸人は賃借人に対し、受領した敷金額から賃借人の債務額を控除した残額について返還義務を負うとされ、賃貸人の優先弁済権を認めました(622条の2第1項)。
②賃貸人は、返還義務の発生前でも、その意思表示により、敷金を賃借人の金銭債務の弁済に充てることができますが(同条2項1文)、賃借人からは弁済充当の請求はできないことが明示されました(同条2項2文)。
つまり、賃貸借契約期間中、滞納している賃料を、賃貸人の側から、敷金から弁済してもらうと言うことはできますが、賃借人の側から滞納分を敷金から引いてくれと請求することはできません。
以上、いずれも、判例法理や従来の一般的な理解を踏まえ明文化されています。
9. 賃貸借契約により生ずる債務の保証について
改正法は、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効としています。この点は、大変重要ですので、保証の部分に詳しく書いています。
10. 経過措置
民法が改正されても、施行日以後、すべての賃貸借契約に改正法が適用になるわけではありません。
賃貸借や保証などの契約については,原則として,施行日より前に締結された契約については改正前の民法が適用され,施行日後に締結された契約については改正後の新しい民法が適用されます。
1. 工事完成前の報酬請求権に関する改正(634条)
請負人は、仕事完成義務を負っているため、仕事を完成させなければ報酬を請求できないのが原則です(旧法632条)。しかし、これでは請負人に酷といえます。
そこで、新法では。
(1)① 注文者に帰責事由なく仕事を完成することができなかったとき、または、
② 請負契約が仕事の完成前に解除されたとき、
(2)既履行部分が可分で、
(3)可分な部分の給付で注文者が利益を受ける場合、
請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる、と規定されました。
2. 請負人の責任:旧法の扱い
旧法第634条が規定する請負人の瑕疵担保責任に関する規定は、以下のとおりです。
① 仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
② 注文者は、瑕疵の修補に代えて、またはその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
上記①の「瑕疵」(欠陥)については、契約で定めた性能を欠く場合またはその物として通常有する性能を欠く場合と解釈されており、
上記①の但し書きについて、瑕疵が重要であれば過分な費用がかかっても修補を要求できると解されていました。
上記②については、注文者は、請負人の能力を信頼できないと判断すれば、直ちに信頼できる別の建築事業者に修補をさせ、修補代金を損害賠償として請求することも可能とされていました。
③ また旧法638条は、請負人の瑕疵担保責任の存続期間について、建物の瑕疵(欠陥)については引渡後5年間、コンクリート造りの建物の瑕疵(欠陥)については引渡後10年間と定めていました。
3. 請負人の責任:新法における見直し
(1)請負人の責任は売主の責任と同様の扱いに
請負人の担保責任に関する旧634条は、削除されました。
新法では、請負契約の仕事の目的物が契約内容に適合しない場合、前述の売買契約の契約内容不適合責任(売買の修補等の責任)の規定(562条から564条)が準用されることになりました(559条)。
そこで、注文者は、請負人に対し、前記売買の売主の責任と同様、履行の追完請求(修補請求)、報酬減額請求、解除、損害賠償請求ができるようになっています。
(2)請負人の責任の存続期間が短くなったこと
注文者の権利行使は、新法では「注文者がその不適合の事実を知った時から1年以内」と変更されました(637条1項)。
ただし、請負人が引渡し・仕事終了時に、その不適合について悪意・重過失のときは、期間制限はなくなります(637条2項)。
4. 新法における請負人の責任の注意点
(1)契約で品質を明確に定めない場合のリスクが高まった
旧634条は削除され、改正民法559条は、前記売主の責任の規定(改正562条等)を準用します。
そして、改正562条は、「引き渡された目的物が種類、『品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき』は、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」と規定しています。
そこで、建物建築請負契約を締結するに当たり、建築する「建物の品質」について、契約書等で明確に定めておかなければ、完成した建物に欠陥があったとしても、そもそも、欠陥≒「契約不適合」の主張自体が困難になりかねません。
(2)修補に代わる損害賠償の要件が厳格に
完成した建物に軽微な初期不良が生じることは、ある程度は避けられませんが、通常大きな問題になりません。
これに対し、完成した建物に看過できない重大な欠陥が幾つも発見された場合、その請負事業者に対する信頼は崩れているので、信頼できる請負業者に修補させたいところです。
前記のとおり、旧法の下では、注文者は、完成した目的物に欠陥がある場合、直ちに信頼できる別の建築事業者に修補をさせ、請負人に対し修補に代わる損害賠償を請求することも可能とされていました(旧634条2項)。
ところが、改正民法は、旧634条を削除し、請負人に対する損害賠償は、改正民法415条によって規律されることになりました。
そして、改正415条2項は、
「債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき、」
と定めています。
ただ、請負人が建てた目的物に欠陥が幾つもあるからといって、修補が不能と断定することは、容易ではありません。
そこで、旧法の下では、完成した目的物に欠陥がある場合、直ちに注文者が信頼できる別の建築事業者に修補をさせ、請負人に対し修補に代わる損害賠償を請求することが困難になりました。
5. 改正法を踏まえた相続・資産活用における注意点
賃貸マンションや住宅の建築は品質ベストの事業者に
改正前から、一生の一大事である賃貸マンションや住宅の建築は、耐用年限・品質(耐火性・耐震性・堅牢さ等)ベストの建築事業者に注文する必要は高かったと言えますが、上記今般の改正により、その必要性は、一層高まったと言えます。
賃貸マンションや住宅の建築に何千万円、1億2億の資金を投じる以上、ベストな品質が契約書に明記され、できる限り修補の必要性が少なく、修補のアフターフォローも万全な、ベストの建築事業者に建築を依頼し、
「改正民法の契約不適合責任のお世話にならないこと」
が是非とも必要であると考えます。
(出典:法務省 説明資料、日本弁護士連合会発行 自由と正義)